設備管理と聞くと「交代制で大変そう」「休みが少ないのでは」といったイメージを持たれる方も少なくありません。ビルや工場、病院など、24時間体制で稼働する建物を支える立場であることから、「土日や祝日でも出勤がある」という印象が先行しやすい職種です。
たしかに、勤務体制によっては夜勤や休日出勤が含まれるケースもあります。ただしその一方で、年間休日120日以上を確保している会社や、完全週休2日制を取り入れている企業も増えつつあります。設備管理という仕事の性質上、勤務時間が明確に分かれている分、しっかりとした休暇制度を整える企業が多いのも事実です。
この記事では、設備管理の年間休日に関する業界の傾向や制度面での違い、働きやすい職場を見極めるポイントについて、客観的な情報に基づいて解説していきます。
設備管理職の年間休日数はどのくらい?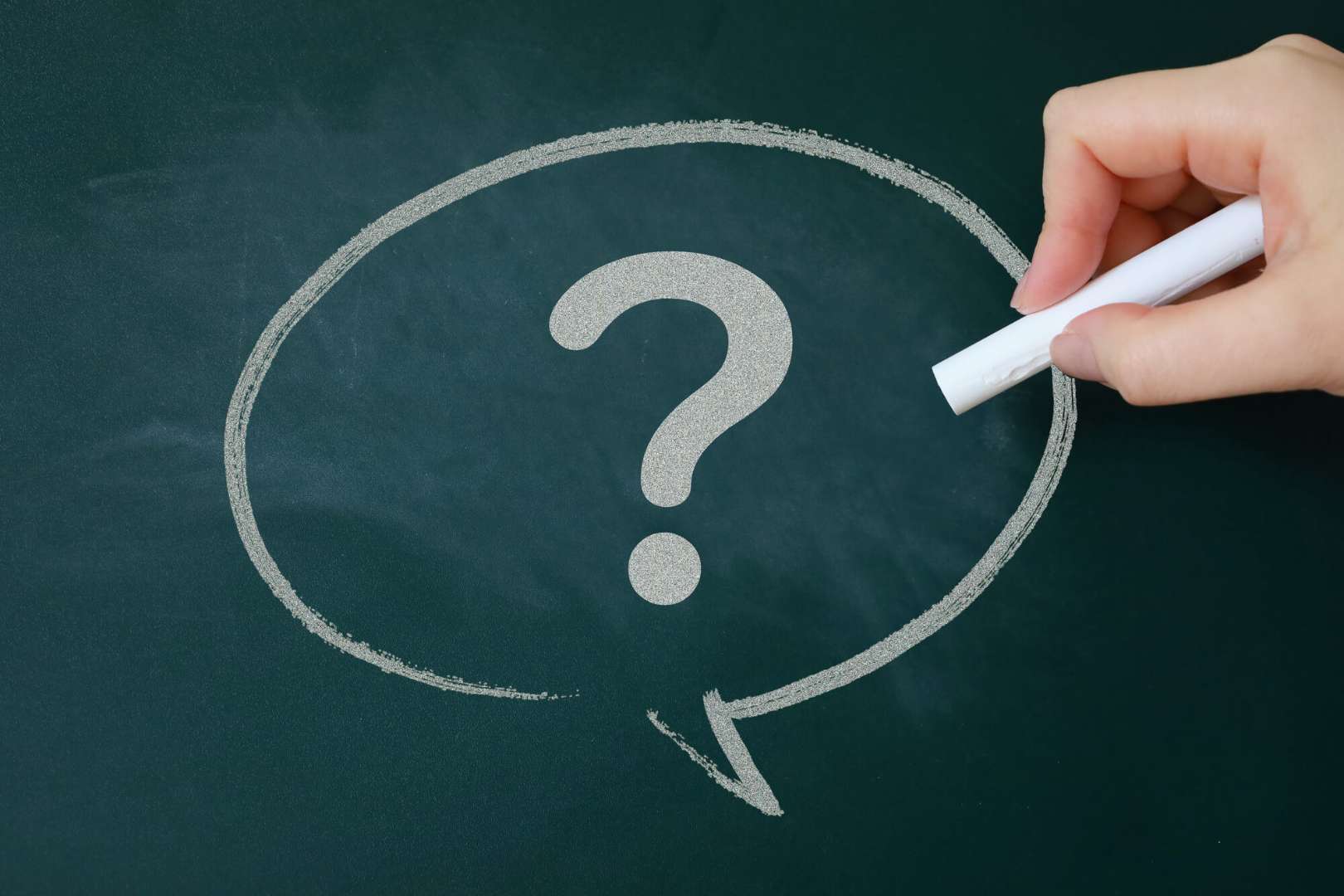
設備管理の年間休日数は、業種・勤務先の種類によって差がありますが、一般的な傾向は明確に存在します。
民間施設と公共施設では休日体系が異なる
オフィスビルや商業施設などの民間物件では、施設の稼働スケジュールに合わせて平日休みを設定するケースが多くあります。一方、公共施設や病院、学校などの場合は、施設が閉館・閉鎖されるタイミングが明確なため、土日休みや長期休暇を取得しやすい傾向にあります。
年間休日の目安は100〜120日以上が標準
厚生労働省の調査や求人情報の傾向を踏まえると、設備管理職の年間休日は「100日〜120日以上」がボリュームゾーンです。完全週休2日制に加えて、年末年始・夏季休暇・有給休暇が取得しやすい環境であれば、年間休日は130日前後に達する企業もあります。実際に「シフト勤務制」と「固定休制」を併用して調整している会社も存在します。
シフト勤務でも実質休日数は確保されるケースが多い
「365日稼働=休めない」わけではありません。交代勤務の制度が整っている企業であれば、夜勤明けや代休制度により、結果として週に2日程度の休みが維持される仕組みがあります。表向きは「変則勤務」でも、年間ベースで見れば十分にリフレッシュできる休日数を確保している企業は少なくありません。
夜勤・シフト制の勤務実態と休日の取り方
設備管理職は、建物の利用状況に合わせて勤務体制が設計されるため、「日勤のみ」の職場もあれば「夜勤あり」「24時間交代制」といった勤務パターンも存在します。
夜勤がある=不規則、ではない
夜勤がある勤務体制でも、勤務スケジュールが事前に定められている場合、生活リズムが整いやすくなるケースもあります。たとえば「夜勤→明け休み→公休」といったサイクルが定着している職場では、勤務後に必ず休息が取れるため、身体的な負担はある程度緩和されます。
勤務形態による休日数の違い
日勤のみの職場では土日祝休みの「カレンダー通り」が基本となり、年間休日は120日前後になる傾向があります。一方、交代制勤務の現場では、月ごとの休日スケジュールが組まれており、曜日に関係なく週2日の休みを交互に取る形式が一般的です。このような場合でも、年間休日は100日以上を維持している企業が多数を占めます。
休日に有給を上乗せできる環境も
設備管理は比較的有給休暇を取りやすい職種のひとつです。理由は「交代制」であるため、事前に人員調整が可能だからです。あらかじめ申請すれば連休を取得できる職場もあり、長期旅行や家族との時間にあてる社員もいます。
働く場所や勤務体系によって「休日の形」はさまざまですが、制度としてきちんと整備されている職場であれば、無理なく働きながら休暇を確保することが可能です。
年間休日で見る“働きやすい会社”の条件
設備管理の仕事は、施設の安定稼働を支える重要な役割ですが、だからといって「休めない仕事」である必要はありません。実際に、働きやすさを重視する企業ほど、休日制度に明確な整備を行っています。
年間休日120日以上は業界の新基準になりつつある
以前は「休日が少なくても我慢」という風潮がありましたが、現在は多くの企業が「人を採用し続けるには働きやすさが必要」と認識しています。そのため、完全週休2日制に加え、有給取得率の向上やリフレッシュ休暇の導入など、休日数の見直しが進んでいます。年間休日120日以上の企業も珍しくなくなりました。
固定休・変則シフトの“見える化”が大切
「カレンダー通り休める会社が良い」とは限りません。シフト制であっても、休日スケジュールが明確に示され、無理な勤務変更がない会社であれば、生活のリズムは安定します。逆に、当日変更や急な呼び出しが常態化しているような環境では、年間休日の数だけでは判断できない働きづらさがあります。
勤務体系の柔軟さ=長く働ける安心感につながる
設備管理は長く働ける職種ですが、家庭環境の変化や体調面を考慮して「日勤のみ」「週末休み」などの配慮ができる会社であるかは重要なポイントです。柔軟な勤務体制を整えている会社は、社員の定着率も高く、職場の雰囲気にも余裕が感じられる傾向があります。
休み方まで見据えた職場選びが、長く続けられる設備管理の働き方につながります。
\協力会社・採用情報はこちら/
https://www.sg-i.jp/recruit_partner
求人票で見るべきポイントと、確認すべき制度
設備管理職への転職や就職を検討する際、求人票には「年間休日〇日」といった表記がありますが、その数字だけを見て判断してしまうのは危険です。制度の内容や取得しやすさまで確認することで、実態に即した職場選びが可能になります。
“年間休日”だけでなく、その中身もチェック
年間休日が120日と書かれていても、それが「完全週休2日+祝日」なのか、「週休2日制(シフト)」なのかで、働き方は大きく変わります。祝日が含まれていない場合や、年間スケジュールによっては連休が少ない場合もあるため、休日の内訳をしっかり確認しましょう。
有給取得率や代休制度の有無も確認
法定の有給休暇制度は存在していても、実際に「取れるかどうか」は会社の方針によって異なります。取得率が公表されている企業であれば、比較の参考になります。また、夜勤や休日出勤に対して代休があるかどうかも、年間の実質休日日数に大きく影響します。
面接や応募前に問い合わせも視野に
求人票に記載のない情報や、制度運用の実態は、面接の場で質問するか、応募前に問い合わせて確認するのも有効です。たとえば「年間休日はどのように確保されていますか」「夜勤明けの休みは休日としてカウントされますか」といった具体的な質問を投げかけることで、会社の姿勢や制度の柔軟さが見えてきます。
勤務条件の“数字”だけに惑わされず、実際の働き方を見極めて選ぶことが、満足度の高い職場選びにつながります。
長く働くなら、“休める職場”であることが大前提
設備管理という仕事は、決して楽ではありません。現場対応、突発対応、施設の責任など、求められることは多くあります。それでも「しっかり休める」職場であれば、その負担は無理なく続けられる程度に変わってきます。
いまや、働き方改革や人材確保の観点から、年間休日や休暇制度の整備は“当たり前”になりつつあります。表面的な勤務条件だけで判断せず、制度の中身、そして現場での実態まで確認して、自分にとって本当に無理のない職場を選びましょう。
働き方のバランスが整った環境でこそ、設備管理の専門性はより深く磨かれていくはずです。
\ご相談・お問い合わせはこちら/


